これもNHK「京都人の密かな愉しみ」の話ですが、各話の終わりにながれる歌(エンディング曲)が奇妙です。まるでお経。まるたけえびすに おしおいけ・・・とか、やわらかい声の呪文詠唱が続いて最後はなぜかシャンソンになる。Je suis née dans cette ville・・云々。
 たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
東から西へバージョンもある。こっちは「てらごこふやとみ やなぎさかい・・」寺・御幸・麩屋・富・柳・堺・・。つまり寺町通、御幸町通、麩屋町通、富小路通、柳馬場通、堺町通・・。
子供のころからこんな唄をうたって、碁盤目の京都の中心部の地名を覚える。迷子にならずにすむ。なるほどねえ。
もうひとつ。解説の地図をながめていると京都には「田の字エリア」という色付き部分があったりする。なんじゃこれは?と不審でしたが、説明をよむと「四条烏丸を中心とした四区画」であることがわかります。道路に囲まれて田の字に見える。つまりは京都の中心の中心です。東京なら銀座四丁目周辺みたいなもんですかね。地価も高い。ここに店を出せれば超一人前。大きな顔ができる。
そうそう。「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」でも、京都の本当の中心はどこなんだみたいなテーマがあったりします。「御所?」と思うのは部外者。何回目かでの説明では、室町の超老舗呉服屋の主人(演・段田安則)がヤマホコ町だとか言明していました。山鉾町。これも調べると「下京区の四条烏丸・室町周辺」らしい。祇園祭で山鉾なんかを出すような町です。
深く追及するとやけに奥深いものがあるんですね、京都は。ま、だからわざわざ京都人をテーマにした奇妙な連ドラができたりする。いまは五輪番組に時間を譲って休んでますが、3月からまた毎週再開だそうです。
※西陣の老舗和菓子屋のおかみが「自分たちは生粋の京都人と思ってるけど、中京・下京あたりの人はどう思っているやら・・」とか言ってました。西陣なんて中心ではないという感覚もあるらしい。この店「どんどん焼け」で焼け出されてひどい目にあったそうです。蛤御門の変のことです。当時のおかみは命より大事な菓子木型の風呂敷背負って足袋はだしで逃げた。
※上述呉服屋主人の自慢では、烏丸通にビル立てた男が、室町に空きができたと聞くと即座にそのビルを売って移転してきた。それほど「室町」は値打ちがあるという証左。京の中心は室町。思いだしたのでメモ。
忘れるだろうから、メモしとくか。あとで振り返ることがあるはず。きっと。
2026.2.8 衆院選 全国的に大雪
| 自民 |
198 → 316 |
維新 |
34 → 36 |
中道 |
167 → 49 |
| 国民 |
27 → 28 |
共産 |
8 → 4 |
れいわ |
8 → 1 |
| 減ゆ |
5 → 1 |
参政 |
2 → 15 |
保守 |
1 → 0 |
| 社民 |
0 → 0 |
みらい |
0 → 11 |
|
|
NHKのBSで1月から「京都人の密かな愉しみ」というドラマ(だろうな)をやっています。そもそもは10年くらい前から始まったもので、いまは3シリーズ目。知ってるようで知られざる京都人の行動や考え方、観光客が知らない風景なんかをを紹介するドラマ仕立 て + 京ルポ + 京料理作り。
大胆かつ不思議な構成なんですが、映像がきれいで女優さんもいい。和服も美しいし、ま、説明の難しい番組です。途中で知って1シリーズの途中から見ています。
 で、いまのシリーズ名は「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」です。老舗和菓子屋をどう継ぐかがメインのテーマ。ソルボンヌからきて、京都御所のすぐ隣の洛志社大学(同志社ですね)に入学した女子学生が慣れない京文化に戸惑っているところです。
で、いまのシリーズ名は「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」です。老舗和菓子屋をどう継ぐかがメインのテーマ。ソルボンヌからきて、京都御所のすぐ隣の洛志社大学(同志社ですね)に入学した女子学生が慣れない京文化に戸惑っているところです。
で、ようやく本題。その洛志社大の教授が渡辺謙です。講義が終わると一人だけの研究室にもどり、やれやれとお茶をいれる。くつろぎの時。
で渡辺教授、最初の回では煎茶をいれました(後では炒り番茶をいれた回もあった※)。その煎茶のいれかた。
(1)スイッチいれて小さなポットで湯を沸かす。(2)熱湯を湯呑(または専用の器)に注いでから腕時計ちらりとみる。(3)煎茶一杯分の紙袋(たぶん)中身をゴボっとフィルターor茶こしに投入。(4)適温の湯をそそぐ。(5)湯呑いっぱいの煎茶が落ちる。で渡辺謙は満足そうに香りをかいでみたり、すこしすすってみたり。
というシーンなんですが、どうもお茶一人前がはいった「煎茶パック」みたいなのがあるように見えました。細かい部分は見逃してるんですが、それをコーヒーと同様、フィルター式に淹れる。面白い。いいなあ。
しかしネットで調べてみると発見できないんですね。見まちがいだったかなあ。市場にあるのはさまざまな「ティーバッグ」だけみたいです。湯呑にいれて湯をそそぐ方式。つまりお茶を粉末にして薄い袋に包んだもの。紅茶と同じやりかたですが、あれ、正直おいしくないです。たぶん上手く味を出せないからかな、抹茶ふうのものを混入してるのが大部分。抹茶ったってもちろん本物の良い抹茶を使う訳がないんで、たぶん安抹茶。色だけ出て、下手すると茶葉をただ粉末にしただけだったり(違ってたらごめん)。
要するに簡単に正しく一人前を淹れられる煎茶ってないんでしょうね。やはり急須を使うしかないのか。
自分は少量一杯だけ飲む場合は湯呑に葉を直接パラパラと入れたりします。すこし時間をおいて、浮いてきた茶の葉をよけながら飲む。決して美味くはないけど、急須を洗ったりする手間がはぶける。でも味気ないしな。なんかイージーでそこそこな方法がないかなと思います。あの色だけ出る「抹茶」はいらない。
※ 二月に入ってからの回では、高級炒り番茶(手炒りほうじ茶)の話もありました。職人の手による高級なもの。安いのとは別物らしい。しらんかった。
「そのうちケーブルを長く」と書いたのが4日前。駅前に買いにいこうと思ってはいましたが、正直、実店舗はあんまり安くないです。貧相なケーブル1本でも1000円以上もしたり。品ぞろえも豊富とはいえないし。
 で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(※)、ちょっと高いのにしてしまった。
で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(※)、ちょっと高いのにしてしまった。
で、届いたケーブルを交換。でかい光電話ルーターと電話をつなぐケーブル50cmを1mに取り替え。光電話ルーターからWi-FiルーターまでのLANケーブル50cmも1mのに交換。色も従来にあわせてます。これで窮屈だったVDSLモデム、光電話ルーター、電話、Wi-Fiルーターの4つ、3D配置がだいぶ楽になりました。
こういう作業って、なかなか楽しいです。
※いつもすまんです。ヨドバシ、ネットショップの評価がえらくいいというなんかの記事を目にして納得。
いまの無線ルータ、当世風に言うと「Wi-Fiルータ」ですか。使い始めてから7年あまりになります。どこといって問題ないんですが、でもそろそろ考えたほうがいい。
たまたま「よかったら使って」とPlalaから貸してもらった(なんでだろ?)ルータがしまい込んであり、偶然ながら同型の機種。NECの WG1200HS3 です。高価ではないですが十分かつ満足で、想像ですが非常に優れたWi-Fiルータだったんじゃないかな。それで当時のPlalaも大量に保有していたとか。たぶん。
ま、そういうわけで豪華なことに予備のWi-Fiルータがある。しまっておいても劣化するだけでしょうし、そろそろ使ってあげようか。古いのが7年。今度のも7年ぐらい使えれば幸せです。
沖の光ルータ(NTT)に繋いだ形で「ブリッジモード」です。つまりルーターの機能は使わず、単なるWi-Fi発信機として使う。ま、ハブですね。
 古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
成功。しっかりスピードも出ています。VDSL(銅線)を介しているんで、これで十分な速度です。ただ機器の配置がすこし不自由。そのうちケーブルを長くしようかな。
いろいろ。
 まずPCの24pin問題ですね。電源ユニットからコードを伸ばしてマザーボードに供給するメインの部分。昔は20pinのプラグ → ソケットだけでしたが、いつのころから電力追加のため「20pin」と「4pin」のプラグを連結して使用するようになった(※)。で、このプラグの差し込みがベラボウに固い。
まずPCの24pin問題ですね。電源ユニットからコードを伸ばしてマザーボードに供給するメインの部分。昔は20pinのプラグ → ソケットだけでしたが、いつのころから電力追加のため「20pin」と「4pin」のプラグを連結して使用するようになった(※)。で、このプラグの差し込みがベラボウに固い。
で、昨年春の新システムから「入らない問題」が発生した。24pinプラグがマザーボードのソケットにきっちり入らない。昔から固いので有名ではあったんですが、それにしてもきつい。どんなにギリギリ突っ込んでもラッチがかかるまで差し込めず、2mmぐらいの隙間です。で、ときどき振動で緩むと電源が入らない。たまに落ちる。危険です。
 延長ケーブル使ってみたり、いろいろやったんですけどね。ダメでした。
延長ケーブル使ってみたり、いろいろやったんですけどね。ダメでした。
理屈からするとそれまでは問題なかったんだから、新しいマザーボードが悪い。しかし間に延長ケーブルをかましてみると延長ケーブルのプラグはマザーボードのソケットにきっちり入ります。そして電源プラグと延長ケーブルソケットの間には隙間。うーん、へんてこりん。要するに以下です。
実例A 「電源プラグ」 → 隙間 → 「マザーボード」
実例B 「電源プラグ」 → 隙間 → 「延長ケーブル」 → 「マザーボード」
これだと電源側のプラグに問題があることになる。つまりプラグに細工をするとか交換するとかで解決。でも以前、同じ電源と古いマザーボードではノートラブルでした。おかしい。
相性というんでしょうかねえ。いじっていると更に隙間があくようになったりして汗でした。しかし何回も何回もトライを続け(しつこい)、軍手はめた指が痛くなったころ、割合スーっと入りました。ん? なんだろ。
「20pin」と「4pin」のプラグの連結具合でしょうかねえ。比較的ピタっと合う瞬間があるらしい。そのタイミングでスムーズに差し込むとわりあい奥まで入る。完全じゃないですが、ま、妥協できる程度のはまり具合です。
納得はできませんが。一応おしまい。やれやれ。
もう一つ。
AI需要がらみでメモリが大高騰です。あおりをくらってSSDなんかも上がるは上がるは。この数カ月で体感2倍くらいかな。自分、いまのところ足りてはいるんですが、調べてみると半年一年ではおさまりそうにもない狂乱高騰らしい。業界構造的なんで下手するともっともっとかかる。うーん、そうか、来年、再来年、今のメモリがそれまで持つかどうか・・・。
さんざんさんざん,千々に乱れて迷った末、思い切って1TBのSSDを1枚、注文かけました。予防措置ですね。あちこち調べてみとメーカーの公式ショップがかなり安い。クーポンなんか使うと他の二割引きくらいの値段になる。どうしてみんな使わないんだろ。
ただ、トラブル報告がけっこうあって、要するに支払い方法がネックらしい。基本的にクレカ支払いなのに、それが通らない、認証エラー。ふーんと読んでましたが、いざやってみたら自分も完全にひっかかった。3Dセキュアとかなんとか、ワンタイムPWが通らない。Firefox、Chrome、Edge、キャッシュを削除したり再起動したり。すべて徒労。
 あきらめて寝ました。翌日、カード会社かサイトサポートに電話いれようと思い、念のためもう一度だけトライしてみたら今度はスルっと通りました。おまけになぜか今度は「ワンタイムPW」を要求されなかったぞ。進み方が昨日と違う。わからん。不思議だなあ。
あきらめて寝ました。翌日、カード会社かサイトサポートに電話いれようと思い、念のためもう一度だけトライしてみたら今度はスルっと通りました。おまけになぜか今度は「ワンタイムPW」を要求されなかったぞ。進み方が昨日と違う。わからん。不思議だなあ。
ま、これで1Tb SSD確保。WD Black SN7100。安心の定番ですね。チューインガムみたいなM.2タイプです。最速Gen5は不要、実際的なGen4で十分です。ほんとは遅いGen3を探したんだけど適当なのがなかった。
※それどころか、さらに追加の別系統8pinとか8pin+4pinとかまで出てきました。必要電力量がどんどん増加してるんですね。電源ユニットも応じて1000Wやら1200Wやら。(私はなるべく電気抑えたシステムにしてます)
※新しくSandisk ExtremeというM.2も出ていますね。Gen4で速度のわりに安いけど、格下のQLC構造なのかどうか詳細不明。ほんと、ちょっと昼寝してると時代が変わる。
最近は本を借り出してもずーっと積ん読状態。結局読み切れに返却することが多くなっています。窓際コーヒーテーブルの上、ダラーっと積まれたまま放置の数冊を見かけるたびに、なんかやましい気分になりますね。なんで読めないんだろ。
 余計に借りすぎかなあと少し数を控えるようになって、最近は二冊程度です。図書館で見て、一応は読みたいなあと思った本で、しかもたった二冊なのに、それでもなおかつ読め切れない。悲しい。
余計に借りすぎかなあと少し数を控えるようになって、最近は二冊程度です。図書館で見て、一応は読みたいなあと思った本で、しかもたった二冊なのに、それでもなおかつ読め切れない。悲しい。
つらつら考えました。ものは試し、いっそ借り出し数をゼロにしてみようか。要するに意図的に飢餓状態をつくる。読む本がない状態にしてみる。読む本がないったって、家の本棚にはうんとこさ転がってるんですけどね。気に入ってわざわざ買いこんだようなのもうんとこさ眠っている(※)。
でまあそんな飢餓状態がずーっと続いたら、もしかしてなんか新鮮な気持ちになるかもしれない。ああ本が読みたーい、とか。すこしくらい文字がかすんだって、目が疲れたって、でも読みたーい。
試してみるか。
※昔古本屋で見つけた獅子文六の堂々たる全集とか、最近では橋本治の長ったらしい双調平家とか、いやいや気軽に読めるものならポール・セローの分厚いやつもある。読み返してみたい文庫なら山ほど。いくらでもいくらでもいくらでもあるぞ。
AI関連が世界中あほみたいなバブルになって、ビデオカードのnVideaは株価が天井知らずです。えーと、いま調べてみたら資産の時価総額が5兆ドルを超えてるらしい。160円計算で800兆ですか。は。(ちなみに日本の予算総額は122兆)
それは、ま、それはカラスの勝手なんですが、あおりでコンピュータメモリが高騰している。半導体メーカーからするとAI向けの高性能メモリ生産に専念したほうが賢い。で、ラインをAI向けに振り向ける。当然ですね。メモリ三大メーカのマイクロンがもうパソコン向けからは撤退とか。大騒ぎです。
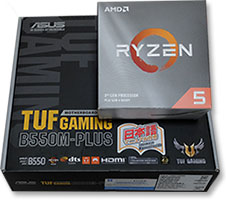 怖いものみたさで価格コム覗いたら、あは、すごいです。メモリはもちろん、その関連おしなべて高騰している。新しいマザーボードの様子を見ておこうと思ってましたが、もう縁切ったほうがいいような世界ですね。いま持ってるCPUやSSD、マザボにはあと4~5年持ってもらわないと困る。かなり決心しないと買えません。
怖いものみたさで価格コム覗いたら、あは、すごいです。メモリはもちろん、その関連おしなべて高騰している。新しいマザーボードの様子を見ておこうと思ってましたが、もう縁切ったほうがいいような世界ですね。いま持ってるCPUやSSD、マザボにはあと4~5年持ってもらわないと困る。かなり決心しないと買えません。
気になって、スーパーでコーヒーの粉とお茶(煎茶)を買ってきました(※)。これも大幅に値が上がっている。必須というか、ゆいいつの楽しみなんで非常に迷惑です。
※コーヒーは240g袋で750円程度。プライベートブランドの煎茶100gも700円台。上がってます。これからもっともっと上がるんでしょうね。困るなあ。そうそう、定期的に買ってる日本酒も値上がりしてます。量は減らしてるけど、これも迷惑です。いまの政府がなんか効果策を打ち出してくれるとはまったく思えないし、困るなあ。
※AIってのは画像認識の世界なんでしょうね。きっと。素人考えですが、すべての事象を「絵」として見ている、きっと。だから画像関連メーカ-のnVideaが注目。パソコン関連でも高性能ビデオカードがずいぶん前から狂喜の高騰です。マニアックなゲームオタクだけが手を出す世界。もう買えない。
まさかと思ってたけど、ほんとにやってしまった。やはり石油が目的なんだろうなあ。平和賞(※)のナントカ女史もそれらしいこと言ってたようだし。
そういう時代になってしまった。欲と我。混沌。ついでに嘘。
※そもそもが、なんか匂うような選賞でした
※追記 : 時間がたつと分からなくなるなあ。えーと、トランプがベネズエラの大統領夫妻を拉致です。ついでですが去年の10月はタカイチがトランプの横でピョン跳ねしました。そのあと「存立危機事態」騒ぎ。すぐ「歴史」になってしまう。
子供は今日のうちに帰るとかで、小型のスーツケース(なんか名称があったような)をゴロゴロ転がして帰宅しました。ん? やはり『帰宅』なのかな。ま、ようするに来週から仕事なんで、準備もあって職場に近い自分の部屋へ帰った。
昨日今日は頼まれてノートパソコンの膨大なデータ移動でした。貸与のPCのためか設定がOnedrive絡みでガチガチ。これがいろいろ不便でローカル環境でも完結できるようにしてほしいとのこと。Onedriveが関係してくるとややこしいです。よくわからん。60Gを超えるデータで、簡単にはコピーできず時間がかかり、なぜかモレが多々あって照合に意外に難航。
とかなんとか。あまりのんびり気分のないままに正月が実質終了です。さて、今日の夕食はさっぱり塩鮭でも焼いてもらうかな。白い飯も(実際には食べてはいるけど)久しぶりのような感じがします。
※はなくて子供に持たせる用に作ったちらし寿司でした。錦糸卵の乗ったやつ
 たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。 で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(
で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて( 古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。 まずPCの24pin問題ですね。電源ユニットからコードを伸ばしてマザーボードに供給するメインの部分。昔は20pinのプラグ → ソケットだけでしたが、いつのころから電力追加のため「20pin」と「4pin」のプラグを連結して使用するようになった(
まずPCの24pin問題ですね。電源ユニットからコードを伸ばしてマザーボードに供給するメインの部分。昔は20pinのプラグ → ソケットだけでしたが、いつのころから電力追加のため「20pin」と「4pin」のプラグを連結して使用するようになった( 延長ケーブル
延長ケーブル あきらめて寝ました。翌日、カード会社かサイトサポートに電話いれようと思い、念のためもう一度だけトライしてみたら今度はスルっと通りました。おまけになぜか今度は「ワンタイムPW」を要求されなかったぞ。進み方が昨日と違う。わからん。不思議だなあ。
あきらめて寝ました。翌日、カード会社かサイトサポートに電話いれようと思い、念のためもう一度だけトライしてみたら今度はスルっと通りました。おまけになぜか今度は「ワンタイムPW」を要求されなかったぞ。進み方が昨日と違う。わからん。不思議だなあ。 余計に借りすぎかなあと少し数を控えるようになって、最近は二冊程度です。図書館で見て、一応は読みたいなあと思った本で、しかもたった二冊なのに、それでもなおかつ読め切れない。悲しい。
余計に借りすぎかなあと少し数を控えるようになって、最近は二冊程度です。図書館で見て、一応は読みたいなあと思った本で、しかもたった二冊なのに、それでもなおかつ読め切れない。悲しい。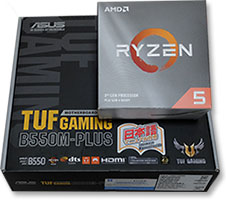 怖いものみたさで価格コム覗いたら、あは、すごいです。メモリはもちろん、その関連おしなべて高騰している。新しいマザーボードの様子を見ておこうと思ってましたが、もう縁切ったほうがいいような世界ですね。いま持ってるCPUやSSD、マザボにはあと4~5年持ってもらわないと困る。かなり決心しないと買えません。
怖いものみたさで価格コム覗いたら、あは、すごいです。メモリはもちろん、その関連おしなべて高騰している。新しいマザーボードの様子を見ておこうと思ってましたが、もう縁切ったほうがいいような世界ですね。いま持ってるCPUやSSD、マザボにはあと4~5年持ってもらわないと困る。かなり決心しないと買えません。