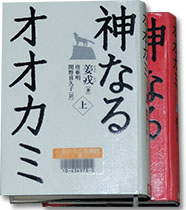
厚い上下巻です。返却期限が迫って、後半は駆け足速読。というより単なる飛ばし読みか。身もフタもない言い方すると、飛ばし読みでもさしたる問題はない本と思います。それなりに面白い本ではあるんですけどね。
えーと、文革で内モンゴルへ下放された知識青年たちが、そこで初めて本物の遊牧文化にぶつかる。羊や馬を養育し、ろくな睡眠もとれずに狼と戦い、冬は厳しい寒さ、夏は酷暑と蚊の襲来に苦しむ。
なんとなくモンゴルはずーっと貧しい草原と思っていましたが、もちろん草が生い茂る地域もあり、湖もある。ただし地表が浅いので、ちょっといじめるとすぐ不毛の沙漠になってしまい、なかなか回復しない。多数の馬がうろうろするだけでもヒズメに掘られて草が枯れてしまうらしい。
テーマは二つ。まず狼の子を掘り出して(メスは深い穴の中で子を育てる)、そいつを育てるというお話。野生狼が犬みたいになついてくれたら楽しいですね。大きくなったらモンゴル犬とかけあわせて新種のシェパードが生まれるかもしれない。
しかし狼の子はいつまでたっても狼です。餌をくれる主人にだけは多少気を許すけれども、それだって場合によっては牙をむく。噛みつく。鎖につながれて気が狂ったように騒ぎ、荷車でひっぱろうとしても死ぬまで抵抗する。絶対に服従しない。
夜、他の狼たちが呼びかける遠吠えを聞いて「ここにいるぞ」と自分もなんとか答えようとします。不器用に遠吠えを試みる。でもたぶん、目のあかないうちに親から引き離された子狼は「狼語」がわかりません。仲間として認めてもらえない。失意のうちに子狼は死にます。
モンゴルの高原では、狼は生態系のトップです。狼が黄羊(モウコガゼル)を食べ、タルバガン(シベリアマーモット)を殺し、野兎を狩る。住民たちにとって狼は天敵です。しかしだからといって狼を殺しすぎると、黄羊や野兎があっというまにはびこる。草原に穴を掘りかえし、草を食い荒らし、そうなると羊や牛、馬の放牧も不可能になる。しかし黄羊や野兎を殺しすぎると狼が飢えて、こんどは馬や羊を襲う。ようするに、バランス。何千年もの間、モンゴルの民たちはその微妙なバランスを崩さないように生活してきた。
しかし南からきた役人や兵士や農耕民たちにその理屈は通じません。草原は広大じゃないか。もっともっと羊を飼え、野兎を殺しつくせ、狼を全滅させろ。農地にしよう。食料増産は国家の大方針だ。指令に抵抗するのは階級の敵だ。そうやって、緑ゆたかだった内モンゴルの高原は沙漠になる。
ま、そういうことですね。かつての知識青年たちは今は都会で暮らしていますが、何十年ぶりに内モンゴルに戻ってみると、もうそこに草原はない。国境線の向こう、外モンゴルにはまだ緑が残っているようですが。
もう一つ。長い小説の最後のほうでは延々と中国史と「狼に学んだ遊牧民族」との関係考察がなされます。中国の歴史は常に「遊牧民族」と「農耕民族」の戦いだった。北の(狼の血をもった)遊牧民族が南に攻め込んで国家を建てる。しかし膨大な農耕文化の漢民族はその猛々しさをすぐに薄めてしまう。狼でなくなった国家は、やがて滅びる。そうやって折々に狼の血をまぜこむことでリフレッシュされ、中国ウン千年はなりたってきた。ま、そういうことです。
たしかに中国史をながめると、中原の北にもたくさんの国家が誕生しています。それが南に攻め込んだり、南から北伐したり。そうやって血や文化がミックスされる。たとえば始皇帝の秦なんてのは、どうみても遊牧民族系ですよね。三国志の曹操の魏だって、なんとなく北方系。元はもちろんそうだし、清もそう。唐もそれっぽい。「歴史をみると、つねに北の国家は南の国家より強い」だそうです。なるほど。
本筋と関係ないですが、大帝国をつくりあげたモンゴルはもちろんモンゴル民族。オスマントルコは突厥。民族大移動の引き金をひいたフン族はたぶん匈奴系だし、そのゲルマンの連中もたぶん遊牧系。さらにいえばローマ帝国も狼の乳によって始まった。帝国はすべて遊牧民族によっておこされた、らしい。