★★★ 中央公論新社
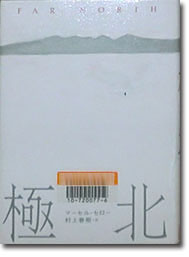
再読。
なんか良質なものを読みたくなったんですかね。良質というと、思い浮かぶのはこの本とか、そうですね、えーと、堀田善衛の「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」、あとはポール・セローの「ダーク・スター・サファリ」ですか。ポール・セローってのは、マーセル・セローの親父です。
そうそう。ヒラリー・マンテルの「ウルフ・ホール」もよかった。
で、「極北」。時間をおいたせいでけっこうストーリーの細かい部分を忘れていました。いい具合。ただし叙述の雰囲気はしっかり記憶に残っています。
人々の死に絶えた極北の開拓村。一人だけ生き延びて、用もないのに警官として周囲を巡邏するタフな主人公メイクピース。もちろん拳銃やライフルを装備して、馬に乗って見回ります。銃弾は自分で作る。1発使ったら、5発補充するのをモットーにしている。なかなか良いシーンなんですが、はて、火薬はどうしていたんだろう。
銃弾とか薬莢なんかは器用な人が時間をかければ自作可能とも思うんですが、パウダー自製は難しいだろうなあ。どっかで大量の火薬樽でも探しあてたんだろうか。ま、そのへんは言いっこなし。
マイナス50度の過酷な環境で人は簡単に死にます。しかし意外にしぶとく生き延びている人もいる。死ぬ人間と生き延びる人間の境目がどこにあるのか。そんなことも考えさせられます。
たまらなく肉が食べたくなると、自家製のウィスキーをソリに積み、数週かけて付近のツングース(ヤクートだったかな)との交易に出ます。仕入れたいのはカリブーの肉など。夏に肉を仕入れてもすぐ腐るので、購入の時期は厳寒期に限る。極北で人々が歩き回るのは厳寒期だけです。蚊もいないし川も渡れるしソリも使える。夏に動きまわるのはバカだけ。夏は必死に作物を育てなければならない短くて貴重なシーズンです。
極北には極北のルールがあります。殺されるのは愚か者。生き延びたければ徹底的に用心し、人を疑う。相手が自分を殺そうとするなら、躊躇なく相手を殺す。神経のピリピリするような日々ですが、それだけに清々しくもある。
作中、主人公は3人ほど、短い期間ながら心を許せる対象を得る。最初はピングと名付けた中国系の逃亡者(子供でしょう、たぶん)。もちろん言葉はまったく通じない。ピングは毎朝太極拳をしたり、怪我を治すために縫い針を耳や鼻に刺したりする。それでも相手は人間です。感情はある。
森の中で出会ったヤクートの少年ともかすかに交流ができますが、ここでも言葉はいっさい通じない。というか、お互い会話をしようともしないし、少年は気持ちをまったくあらわない。ずーっと無表情。ただ、なんらかの感情のつながりがあったような印象は残る。
後半、もう一人の友人(らしきもの)も生まれます。ただし、これも本当に心を許せるかどうかはわからない。おまけに英語圏の人間ではなくイスラムで、科学知識があり何カ国語もマスターしている教養人。彼は苛立ってメイクピースを「野蛮人」と罵ります。たしかにメイクピースは野蛮人です。街を知らない。文化にも縁がない。本もほとんど読まない。ただ知っているのは厳しい土地で生き延びるためのノウハウとタフな生命力だけ。
こういう主人公を据えた本って、読んだことがないような気がします。メイクピースは非常にシンプルです。時折、深く考えることもあるけど、それ以上は追求しない。まず生きること。少なくとも無様な形で死ぬのはいやだ。父親はインテリで一国の大使とも議論できそうな人でしたが、実生活においては釘一本まっすぐ打ち込むこともできない。メイクピースは逆です。教育はほとんどゼロ。しかし釘は打てる。銃も使えるし馬にも乗れる。厳寒の極北を何週間も一人で旅することもできる。
文明とか教養って何なんだろうか。知識はもったほうが幸せになるのか、むしろ無知のほうがいいのか。いろいろ考えさせられます。いずにれしてもこの小説、感傷はゼロなんですね。清々しい。