今年は雑読エントリー数が75。少ないです。★★★★評価なんてあったかな?と検索かけてみると、それでも一応はありました。えーと8冊ですか。ま、そんなもんでしょう。
「三四郎」 夏目漱石

なんで読もうと思ったのやら。田舎青年が東京に出てきてマゴマゴする姿が楽しい。気負いやら気後れやら狼狽やら。青春小説ですね。そうそう、なぜか人気らしい「坊ちゃん」、こっちを青春小説と称するのは奇妙な気がします。ついでには言えば「心」もあまり感心しません。漱石らしくない。
ただ若い頃の読み方と年取ってからでは変わりますね。子供の頃は美禰子さんが神々しく映った気がします。落ち着きはらって胆がすわって、若い女とは思えない。小説なんだから当然、三四郎と美禰子は恋愛関係になるんだろうと思っていたら、あれれ、なんか変だなあ。
人生経験経てから読むと、なーんだ、若い三四郎はからかわれているんだ。からかうという言い方は少し違うかな。要するに美禰子に振り回されている。ただし美禰子が自覚して男どもを振り回しているとは限らない。天然自然、それが「女」なのかもしれない。三四郎がグイッと迫ったら、ひょっとしたらの可能性があったかもしれないし、ダメだったかもしれない。
野々宮さんの妹でしたっけ、頭の鉢の開いたよし子。どこにも美人と書かれていないし、よし子が三四郎に好意を持っているとも書かれていない。でも読んでいるほうとしては、勝手にそう受け取ってしまう。面白いものですね。こういう小説はやはり★★★★にするしかないです。
「醒めた炎 木戸孝允」村松 剛

久しぶりに全巻通して読みました。とにかくマメで気がついて親分肌で忙しい人だった。充実しているともいえるし、生き急ぎすぎたともいえる。享年45。イライラして胃を悪くして、たぶん怒り狂いながら死んだ。
何回も書いてますが、明治の最初の10年間、よくまあ国家の形を保てたものです。薩長の政治家・首脳はみんな若僧で思いつきで自分勝手に動き回って、よくまあ国が潰れなかった。酷税に苦しんだ国民、よくまあ我慢した。もちろん暴動や蜂起もあったようですが、組織だったものに発展しなかったのが不思議なくらいです。明治維新とこの明治初期、ものすごいラッキーに恵まれたんでしょう。
話は違いますが、最近は関ヶ原の勝敗も、どうも「運」の固まりだったような気がしてきました。事後評価としては西軍の戦意のなさとかグズグズぶりが強調されますが、双方の陣構え図をみると、どう考えたって家康が突出しすぎている。本陣のあった桃配山ってのは、常識外れに西に寄った場所なんです。わざわざ自分から袋のネズミになっている。ずーっと東の南宮山にいた毛利とか長宗我部なんかが、もし気を変えて(可能性は十分ある)その気になれば完全な包囲・殲滅戦になっていた。
ただ、実際にはそうならなかった。吉川広家は動かなかったし、広家が動かないので毛利秀元も山の上に留まっていた(宰相殿の空弁当)。気の利かない長宗我部もボーッとしていた。そして決断を伸ばしていた小早川も最終的には動いた。ま、そういうことです。結果的には「さすが神君」と家康は祭り上げられますが、本当はかなりヤケだったんじゃないか。イチかバチかの賭が当たった。
大きな戦とか国家運営とか、たまたまの偶然とかラッキーがあんがい大きな要素になるのかもしれないです。ユゴーのワーテルロー戦評価に通じますね。前日からの雨で砲車が動けなかった。援軍として駆けつけるべきグルーシー元帥が気の利かない男だった。気圧の具合でお腹の疥癬が悪化したウンヌン。
「大聖堂」レイモンド・カーヴァー
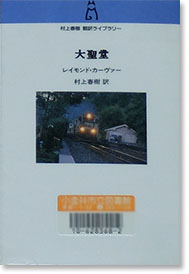
村上春樹がよくひきあいに出すレイモンド・カーヴァーの短編集です。
どういう筋でどういう内容・・と詳細を書いても仕方ないような作家ですね。ひたすら雰囲気だけで読ませる。これといってオチがあるわけでもないし、特に叙情的というものでもない。ほんと、説明しにくいです。そうそう、表題作の「大聖堂」は、あんまり好きになれませんでした。
ちなみに書かれている題材はほとんどがアル中、離婚、失業などなど。日常が少しずつ壊れていく。読後感は悪くないけど暗いです。★4評価は甘くて、実質的には★3と★4の中間くらいかな。
「日本はなぜ基地と原発を止められないのか」矢部宏治

故ハマコーが喝破したように「アメリカ様に逆らえない」はなんとなくの常識ですが、では日本は米国の植民地なのか。そこまでではないにしても「準属国」なのか。
実際には、ことあるごとに米国や米軍が口出ししてくるわけではないようです。そこまでは露骨ではない。しかし「安保法体系」なるものが戦後の日本を支配してきたのは事実。具体的には日米安保とか地位協定とか密約とか、細かなことなら日米合同委員会とか、複雑に糸が張りめぐらされている。事実上、こうした「体系」に逆らうような動きは不可能なんだそうです。すべてが米国の強制ではなく、日本側からの追従・迎合も多い。
仮に政府の専断に怒った民間団体が訴訟を起こしても、政府は絶対に負けない。負けないような形が整っている。だから役人は強気で行動する。役人は負ける側には決して立ちません。おまけに司法は最終的に必ず味方をしてくれる(高度に政治的な事柄に司法は関与しないという最高裁判決がありますね)。そういう形を戦後数十年、しっかり作り上げてきた。なるほど、という説明でした。
ちなみに意外だったのは日本上空の管制権。けっこうなパーセンテージのルートが米軍専用で、日本の旅客機は立ち入り禁止(だから羽田発の航空機は海側に出て行く)。これは知っていましたが、本当は「米軍機は日本上空すべての飛行権をもつ」のだそうです。
ついでですが、米国が日本を守っていると考えるのもかなり甘い。どっちかというと「日本が敵対しないように監視している」というのが近いんじゃないだろうか。ちなみに国連には「敵対国条項」がいまだに残っているんだそうです。日本とドイツは敵対国。これがまた戦争を起こさないように監視するのが国連本来の役目でした。
「連合軍」はUnited Nations、「国連」もUnited Nations。つまり国際連合などど綺麗な言い方ではなく本当は「連合国連盟」とでも称したほうが実情に合っている。それなのに敵対国の尻尾を引きずっている日本が常任理事国になろうと運動しているらしい。奇妙な状況なんでしょうね。
「お言葉ですが別巻6 司馬さんの見た中国」高島俊男

この人のはたいてい面白いですが、すぐ漢字やら言語の話になるのが困る。それが専門なんだから仕方ないですが、やはり漢字絡みの話になると内容がなかなかに難しい。その点、この別巻6は比較的読みやすいです。
高島俊男という人。とにかく「やりすぎでしょ」と心配になるぐらい権威を切りまくる御老人です。作家や評論家を叩く程度ならわかりますが、飯のタネである大手出版社まで攻撃する。そりゃ敬遠されるでしょうね。ただその切り方が痛快無比で遠慮がなく、ついニヤリと笑ってしまう。
この一冊もいろいろなテーマが盛り込まれていますが、たとえば日本で歴史を贋作というか、強い影響力、勝手なイメージを作り上げてしまった元凶は3つあり、日本外史、司馬遼太郎、NHK大河ドラマなんだそうです。これは非常に納得でした。
ついでですが、日本の「儒学」はいちおう幕府から公認厚遇されていたようですが、実際にはクソの役にもたたない。その代わり害毒ももたらさなかった。それに対して国学は一見マイナーふうなのに浸透力があった。困ったことになまじ影響力をもったために非常に害をなした。本居宣長とか平田篤胤一派でしょうね。これも非常に納得しました。
「戦争と平和」トルストイ
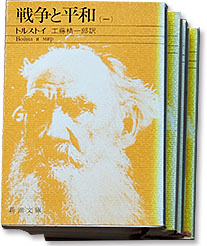
うーん、これを★★★以下にするわけにはいかないよなあ・・という理由で★4です。そこが「名作・古典」というもの。
それにしてもこの歳でよくまあ再読しようなんて考えた。同じような「名作」でも、たとえばば罪と罰をまた読もうという気にはならない。同じトルストイでもアンナ・カレーニナや復活なんかは手をつける気にならない。大昔、つい懐かしくてジャン・クリストフを買ったけど、いまだにページを開いていない。その代わりモンテ・クリスト伯は何回も読んでいるしレ・ミゼラブルもけっこうな回数読んだ。どこが違うんでしょうかね。
で「戦争と平和」、久しぶりに読んで、やはりナターシャはあんまり好きになれなかった。ついでにピーターってのも、昔からあまり好感持っていません。アホくさい。ま、そんなことは作者が百も承知のわけで、それでも読ませるのが名作の所以なんでしょう、きっと。
だんだん好きになるのは強欲なワシーリー公爵とかヤクザなドーロホフ。ボリスという青年もけっこう好きです。そうそう、ナターシャの姉さんと結婚したケチな男もいいですね。名前は忘れましたが実に似合いの夫婦。
それはそれとして、なかなかに面白い本でした。読んでよかった。最初に読んだのが大学受験後の春休みで、ようやく読めるぞォーという解放感。何日かかったのか。コタツに座りっぱなしでずっしり重い筑摩の細かい活字にとりつきました。読み終えてしばらくボーッとしていた記憶がある。
大昔の大学の一般教養(般教)でとった国文学概論、当時人気だった助教授が「名作ってのは、読み終えると1週間くらいはボーッとするもんです。世界が変わる」とか言うていました。納得です。
「マオ 誰も知らなかった毛沢東」ユン・チアン

例の「ワイルド・スワン」のユン・チアンです。意外な事実が多かった。というより自分が何も知らなかったというべきかな。
例の長征、単なる逃亡だろうとは思っていましたが、なぜその結果として共産党が大きな力を得たのか。そこのところが分からなかった。不思議です。
この本で理解した限りでごく大胆に言うと、まず国民党が自壊した。失望を買ったんですね。それに代わるものは何か?というと、可能性として共産党しかない。
そんな中、地方組織から権謀術数の限りを尽くして毛沢東がのし上がってきた。方法はシンプルで、とにかくハッタリと嘘。思い切って大胆にやります。そして反対派を徹底的に殺した。もちろん文句をいう農民も無慈悲に粛清。権力を握った。独裁ですね。そして田舎に籠もったため、都会の若者たちには実態が伝わらず、まるでマルクス主義の理想郷のように喧伝された。
ちょうどオーム教団です。腐敗した国民党に絶望し、熱に浮かされた都会の青年たちが延安に吸い込まれていく。そこから(生きて)出てくる連中はいない。神話だけが先行して中身が見えない。実際には逃げようとした連中はたくさんいたけど、みんな殺された。不思議な熱気があったようです。
毛沢東という人、やはり天才なんでしょうね。嘘を言うことに躊躇がない。邪魔になる連中を抹殺することにもためらいがない。いかにも恨みをかって暗殺されそうですが、見事なくらいに臆病で保身に走る。そしてひたすら宣伝々々。宣伝し続ければ嘘も真実になる。
例の大躍進。農民がどんどん餓死した理由の一つは、失政でただでさえ乏しい食料を海外輸出し続けたからのようです。ソ連から高価な武器を買いたいけど、貧しい中国にはほかに輸出するものがなかったから食料を売った。その結果人々が死ぬことにまったく関心がなかった。1億死のうが2億死のうが、それがどうした。(悪い意味で)傑出した人間です。
そうした毛沢東に抵抗する者はいなかった。いたことはいたようですが、みんな途中で(周恩来のように)くじけた。くじけなかった者は抹殺された。
「老生」賈平凹

中国にも素晴らしい作家はたくさんいる。ひょんなことから莫言を読み始めたのがキッカケで、高島俊男さんの紹介する作家リストなどを参考に、図書館で発見するたびに少しずつ読んでいます。この賈平凹もいい作家でした。
「老生」は年齢不詳の弔い師(弔い唄をうたうのが仕事)を狂言回しに、国共内戦、土地改革と人民公社、文化大革命、そして開放期。一つの村に住む人々の愛や欲望や憎しみ、殺し合いをずーっと追ったものです。現代中国ではこういう大河スタイルの小説が非常に多いですね。他に書きようがないのかもしれない。党を直接批判せず、しかし婉曲にでも抵抗の姿勢を見せるのは非常に難しいのだと思います。
そうそう。記述の背景として、山海経(せんがいきょう)の読解があります。意図がわからないし成功しているとも思えないのですが、たしかに奇妙な本らしい。まさに怪書。ひたすら天下の山や海、そこに住む怪物や産する鉱物を延々と記述している。こういう内容の本だったのか・・と知っただけでも凄い。ほんと、中国にはなんでもある。
「群雲、関ヶ原へ」岳宏一郎

関ヶ原ものの定番ですね。登場人物がいったい何人いるのか。それぞれの武将がそれぞれの思惑で必死に生き残りをかける。卑怯な奴もいるし、バカ正直もいる。うまく成功した武将もいるし、なぜか失敗してしまったものいる。文字通り「命をかけて」の駆け引きであり、どっちが勝つかの読み勝負。そうした大小の「群雲」たちが関ヶ原の一点へ向けて収斂していく。司馬遼太郎とはまた違った味で、傑作と思います。
登場する人物みんなが必死に生きているからか、読後感は爽やかですね。家康は不器用で愛嬌があるし、三成はもっと不器用で傲岸不遜だけど、可愛いところもある。完全なヒーローなんていないし、悪人も敵役もいない。唯一、上杉景勝だけがちょっと綺麗に描かれすぎで、これは作者のエコヒイキでしょう。
さすがに何回も読みすぎて、どこかの章を読み出すと「ああ、こういう話だったな」とすぐ思い出す。すぐ思い出してしまうのは詰まらないですが、それでも時折は読み返す本です。