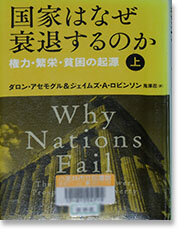 早川書房 ★★
早川書房 ★★
かなり話題になった上下本です。何カ月待ちの予約をかけてしまった。
で、国家はなぜ衰退するのか。地理的要因ではないし、気候要素でもない。人種、文化でももちろんない。
では何か。国家の体制・制度で、収奪的か包括的かが大問題。つまり「収奪的制度」の国家なのか「包括的制度」の国家なのかで決定されるという。
なんの話じゃ? 収奪的というのは王や政府が国民から基本的にむしりとる体制です。ま、歴史的に見てたいていはそうですね。王や政府ってのはそのためにあるんだから。で、中央集権的、収奪的な体制はある程度まで有効です。無政府状態にくらべれば、はるかに効率がいい。
しかし、ある程度までいくと、発展がとまる。ローマ帝国は停滞した。中華もソ連も止まった。王や政府にとって「発展」にあまり意味・利益がなくなるからです。今のままで十分じゃないか。インセンティブの欠如。だから鄭和の大船団は無駄に燃やされた。
筆者たちによると「包括的制度」では国民の多くにインセンティブがある。参加し努力することに意味がある。むくわれる可能性がある。名誉革命後の英国がそうなんで、結果として産業革命。努力すれば豊かになれるかもしれない。逆にいうと、既存の支配階級が、この連中の押さえこみに失敗した。
日本では明治維新。薩摩の大久保と薩摩斉彬が偉かったらしい。この二人と、ついでに坂本龍馬。ふーん。身近なことになると、書き手の調査量がよくわかります。なぜか斉彬。
ま、ともかく。要するに「収奪的制度」から「包括的制度」に脱皮できれば発展する。できないとずるずる沈む。米国はできた。オーストラリアもできたんだそうです。フランスは革命で大脱皮したし、逆に「収奪的制度」に逃げた国もある。アフリカの大部分、中南米の国々。アジア。みーんな成功しなかった。もっと正確には脱皮を妨げられたケースが多い。
で? が問題ですね。「収奪」から「包括」への道は偶然です。どうしたら脱皮できるのかは、この本の主題ではないらしい。この国はこんな経緯で成功した、この国はこんな経緯......。このエピソードが延々と続く。でもどうしたら「そうなれるのか」はわからない。
かなり、不満が残ります。